原題:“Richard Jewell” / 原作:メアリー・ブレナー / 監督:クリント・イーストウッド / 脚本:ビリー・レイ / 製作:ジェニファー・デイヴィソン、レオナルド・ディカプリオ、ジョナ・ヒル、ジェシカ・メイヤー、ケヴィン・メイシャー、ティム・ムーア / 撮影監督:イヴ・ベランシェ / プロダクション・デザイナー:ケヴィン・イシオカ / 編集:ジョエル・コックス / キャスティング:ジェフリー・マイクラット / 音楽:アルトゥーロ・サンドヴァル / 出演:ポール・ウォルター・ハウザー、サム・ロックウェル、キャシー・ベイツ、オリヴィア・ワイルド、ブランドン・スタンリー、ライアン・ボズ、チャールズ・グリーン、ジョン・ハム / マルパソ製作 / 配給:Warner Bros.
2019年アメリカ作品 / 上映時間:2時間11分 / 日本語字幕:松浦美奈 / PG12
2020年1月17日日本公開
公式サイト : http://richard-jewell.jp/
TOHOシネマズ日比谷にて初見(2020/01/23)
[粗筋]
リチャード・ジュエル(ポール・ウォルター・ハウザー)は以前から法執行官になることを夢見ていた。官公庁の備品管理の仕事をしながらも、如何にしてひとを守るべきか、を学ぶのに余念がない。肥満体で自己アピールも乏しい彼を気にかける者は少なかったが、唯一、弁護士のワトソン・ブライアント(サム・ロックウェル)だけは彼の繊細な気配りを評価した。警察官になるための一歩として、警備員への転職を決めたリチャードに、ワトソンは100ドルを餞別として渡す。リチャードは、警官になったときは、初任給で必ず返す、と約束した。
しかし、ルールや安全のためにしばしば暴走するリチャードは、なかなか職場が定まらないことに悩む。折しも地元アトランタで開催されたオリンピックに合わせ、記念公園で連日セレモニーが催されており、リチャードもどうにかその現場の警備員として勤めることになった。
事件は1996年7月27日に起きた。撮影スタッフや音響機器が集められたタワーのそばで、酔った若者たちを注意して追い払ったリチャードは、ベンチの下に押し込まれた鞄を発見する。不審物と判断したリチャードは現場に詰めていた警察官に報告、半径30メートル以内からひとを避難させるように進言した。警官達は重大性を疑いながらもルールに従い、周辺の人びとを誘導するかたわら、不審物の中身を調べる。
リチャードの予想通り、中身は爆弾だった。リチャードも協力し、急いで周囲からひとを遠離けているそのさなかに、爆発が起きる。
爆弾には釘が仕込まれていた。そのために死者も含む多くの犠牲を出したが、もし発見されていなければ被害はこの程度では済まない。周囲はリチャードを褒めたたえ、警備会社も彼を“ヒーロー”として積極的に露出させた。自分だけでなく、自らも負傷した警察官もまたヒーローだ、とリチャードは謙遜するが、彼が法執行官に憧れ続けていることを知る母ボビ(キャシー・ベイツ)は誇らしかった。
本の出版の話さえ舞い込むほどだったが、母子の歓喜は僅か3日で覆される。アトランタの地元紙がFBIから得た情報として、リチャードを第一容疑者として捜査対象にしている、と報じたのである。
自宅の周囲にはマスコミが集まり、外出のたびに容赦のない質問をぶつけてくる。FBIは捜査協力と称して、リチャードに“犯行”を再現させようとした。この奇妙な扱いに困惑したリチャードは、出版の話が舞い込んだとき、はじめて連絡を取ったワトソン・ブライアントを頼った――
[感想]
この梗概を聞いたとき、私が咄嗟に思い浮かべたのは、本邦のいわゆる“松本サリン事件”だった。あちらは毒薬が撒かれた現場がたまたま近かったことから嫌疑をかけられたのだが、それが報じられてからの世間の反応が似ている。大きな悲劇に際して、ひとびとは嘆き、犯人に対する憎悪を膨らませるが、しかしその感情が向けられる対象が誤っている可能性については考慮を忘れがちだ。
本篇の事件が起きた当時、犯罪捜査の現場では“プロファイリング”が偏重される傾向にあった。犯行の内容から犯人の特徴を分析し、それに当てはまる人物を探す。確かに効力を発揮した時期はあったようだが、そこには本篇でも仄めかされていたような落とし穴がある――プロファイリングされた人物像に囚われるあまり、他の手がかりや証拠を軽視してしまうと、抜け出せなくなる。
恐ろしいのは、怒りと正義感に駆られるあまり、多くの人間がほかの可能性を追わなくなってしまうことだ。この作品で観る限り、そもそもジュエルには犯行に及ぶ理由はおろか、その機会すらなかったことが明白なのだが、その事実をまともに検証しようとしたのは弁護の依頼を受けた弁護士だけで、マスメディアはおろか捜査機関すら顧慮しない。狂騒的な思い込みだけで、抵抗する力の乏しい個人がその生活ごと追い詰められていくさまは慄然とする。
本篇は序盤、爆破事件に至る経緯をジュエルの視点で描き、それ以降もブレることなくほぼジュエルの目線で描写する。それ故に、観客の目にはジュエルの無実はほぼ明確であり、それだけに余計マスメディアや捜査機関の執拗な追求の理不尽さが際立つ。そして、味方につくブライアント弁護士の頼もしさも引き立っている。
どの程度現実に沿っているのかは謎だが、事件の起こる以前から理解者としてブライアント弁護士がいたことは彼にとってもっけの幸いだった。こういう立場に置かれたとき、如何に法律を熟知しているか、或いはそういう味方をつけるのが大切かがよく解る。言質を引きだそうとするひとびとに対抗するには、まず沈黙し、手が緩んだ隙に自らの主張を提示して反撃する。
孤独だが好人物そのもの、というジュエルに対し、ブライアント弁護士はかなり風変わりだ。はじめはどこか狷介そうだが、すぐにジュエルの人柄を理解し受け入れる。時を経て突然ジュエルから専門外の依頼があったことに戸惑いながらも、自身のスキルを駆使して彼を救おうとする。言葉遣いも振る舞いも乱暴で、最初はジュエルが果たして無実なのか、も疑うが、いったん信じたあとはひたすらジュエルの名誉を守ろうとする。そのためにはジュエルにさえ厳しい言葉を吐き、あえて怒りを誘うことも厭わない。もともと個性と実力を備えた俳優として業界からの信頼は厚かったというサム・ロックウェルだが、オスカー獲得以降はより充実した仕事ぶりを見せており、本篇と同時期に発表された『ジョジョ・ラビット』ともども非常にいい味を出している。
この物語に救いがあるとすれば、ジュエルの人間性そのものだろう。普通の人間よりも過剰に法執行官に憧れているきらいはあるが、いい意味でも悪い意味でも凡庸な人物像だ。だからこそ、爆発物を発見した際に率先して行動し、英雄扱いされて天狗にもなる。だが、理不尽に嫌疑をかけられ捜査官にもマスメディアにも包囲される状況に、当然のように激しいストレスを味わう。冒頭から描いているからこそ、ジュエルの常識的な感覚が理解できるし、過熱する事態に動揺する姿にも説得力がある。そして、暴力などの過激な手段に走ることなく、真っ当な主張で以て正しい結末を勝ち取る。展開としての派手さはないが、その決着が清々しいのも、彼のこういう人柄と着実な支えがあったからだろう。
近年、実話に取材した作品が多いクリント・イーストウッド監督だが、本篇においては『運び屋』のように自分が画面に出ることも、『アメリカン・スナイパー』のように象徴的なクライマックスを加えることなく、外連味を抑え淡々と綴っていく。しかし、まったく迷いのない構図や、リズムを保ちつつも堂々たるテンポのお陰で、決して派手ではない物語に風格が漂い、作品に厚みが備わっている。キャストに対してもスタッフに対しても充分な信頼を持ち、持たれているからこそ、このシンプルな物語がパワフルな傑作に仕上がったのだと思う。
関連作品:
『チェンジリング』/『ハドソン川の奇跡』/『15時17分、パリ行き』/『運び屋』
『月に囚われた男』/『カウボーイ&エイリアン』/『ジョジョ・ラビット』/『ミッドナイト・イン・パリ』/『サード・パーソン』/『エンジェル ウォーズ』
『狼たちの午後』/『ブラック・サンデー』/『ユナイテッド93』/『誰も守ってくれない』/『フライト』/『ラビング 愛という名前のふたり』

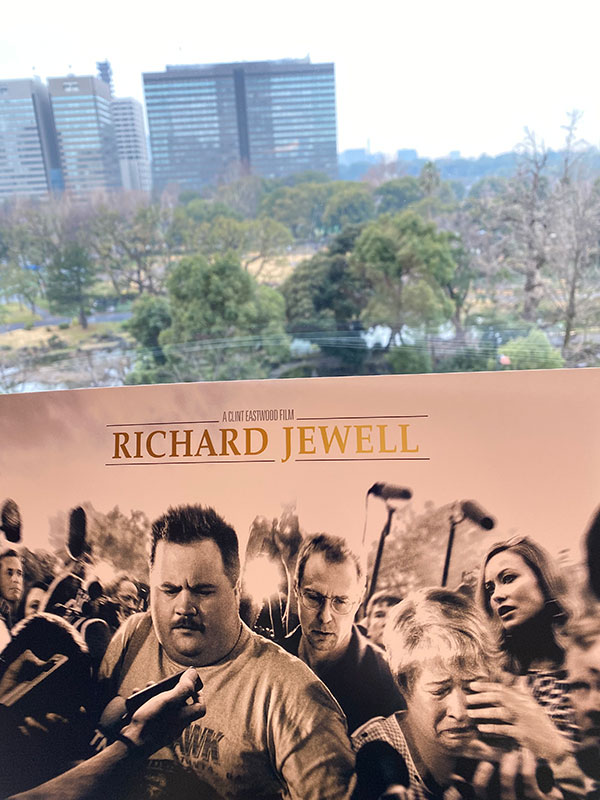


コメント