原題:“In the Line of Fire” / 監督:ウォルフガング・ペーターゼン / 脚本:ジェフ・マグワイア / 製作:ジェフ・アップル / 製作総指揮:ウォルフガング・ペーターゼン、ゲイル・カッツ、デヴィッド・ヴァルデス / 共同製作:ボブ・ローゼンタール / 撮影監督:ジョン・ベイリー,A.S.C. / プロダクション・デザイナー:リリー・キルヴァート / 編集:アン・V・コーツ,A.C.E. / 衣装:エリカ・エデル・フィリップス / キャスティング:ジャネット・ハーシェンソン,C.S.A.、ジェーン・ジェンキンス,C.S.A. / 音楽:エンニオ・モリコーネ / 出演:クリント・イーストウッド、ジョン・マルコヴィッチ、レネ・ルッソ、ディラン・マクダーモット、ゲイリー・コール、フレッド・ダルトン・トンプソン、ジョン・マホーニー、クライド草津、ジョン・ハード、トビン・ベル / 配給:コロンビア・トライスター映画 / 映像ソフト発売元:Sony Pictures Entertainment
1993年アメリカ作品 / 上映時間:2時間8分 / 日本語字幕:菊地浩司
1993年9月15日日本公開
2010年4月16日映像ソフト日本最新盤発売 [DVD Video:amazon|Blu-ray Disc:amazon]
[粗筋]
かつてケネディ大統領暗殺を阻止し損ねた、という負い目を残しながら、未だ現役でシークレット・サービスに奉職するフランク・ホリガン(クリント・イーストウッド)は、通報を受けて一軒のアパートを訪ねた。しばらく連絡が途絶え、大家が踏み込んで異常に気づいた、というそこには、かつての大統領暗殺に関する記事が壁を飾ってあった。
アパート契約の際に残した書類はすべて偽装で、身許を探り出すことは出来なかったが、間もなくアパートの主から連絡が届いた――他ならぬ、フランクの自宅に、である。男は既にフランクの前歴を調べ上げており、まるで古くからの友人であるかのような口調で、不敵な挑戦状を叩きつけてきた。長年の勘で、この男が本気で大統領暗殺を目論んでいる、と確信したフランクは、志願して大統領の身辺警護の任に着いた。
折しも、次期大統領選の選挙運動が始まっている時期であり、大統領はキャンペーンのために各地を飛び回っている。現場を離れて久しく、肉体的にも衰えているフランクにとって、活発に動き回る大統領の警護は重労働だった。雨のなかの演説に立ち合ったのがとどめとなり、体調を崩したフランクは、風船が割れる音を銃声と勘違いし、衆人環視の前で大統領に恥を掻かせてしまう……
[感想]
実は、クリント・イーストウッドのフィルモグラフィにおいて、特異な位置づけにある作品である。本篇以降、2012年の『人生の特等席』まで、イーストウッドは自身以外が監督した作品に出演していない。また、本篇は彼の出演作では極めて稀な、自身の製作会社マルパソの名前がクレジットされていない作品でもある――製作総指揮には、製作会社のパートナーであるデヴィッド・ヴァルデスの名前があるので、まったく関与していなかったわけではないだろうが、マルパソの名前がないのはやはり稀有だ。
背後にどんな事情があったのかは解らないが、しかし本篇を観ていて、そういう違いはほとんど意識しないし、恐らく意識する必要もない。いい意味で気負いなどない、正統派の娯楽サスペンス・アクションに仕上がっている。
要素はほとんど定番だ。振る舞いはハードボイルドだが、悔恨拭いがたい過去を背負った主人公。不気味に暗躍する危険な敵。両者の駆け引きが随所で描かれる一方、年齢や境遇にも起因するトラブルが絶え間なく主人公を襲う。若くいささか頼りないが誠実な相棒を巡る展開も、王道ながら効いている。まったくひねりがない、という批判もあるだろうが、しかしそれ故の安心感と、しかし要素を無駄にしていないからこその緊張、ハラハラドキドキを演出する手管の巧さは間違いなく評価されて然るべきだ。
イーストウッドを起用する、ということが先に決まっていたのか、シナリオや本篇の主人公のアイディアが先にあってイーストウッドに着目したのか、どちらかは解らないが、この主人公像はイーストウッドがこれまで演じてきたキャラクターの線上にきっちりと乗っている。そのうえで、犯人像との噛み合わせも絶妙だ。背景に似通った部分があり、表裏一体となっているからこそ生まれる感情の起伏が、物語をもうまく揺さぶっている。若い相棒や、当初は相容れないムードを漂わせる女性の同僚とのロマンスも、お約束だが無駄は感じない。
穿った見方をすれば、本篇はこの当時のイーストウッドが至った境地ゆえの、余裕が生み出したものかも知れない。自ら監督・主演した『許されざる者』がアカデミー賞に輝き、いわばひとつの頂点に達した直後である。自身の作りたいものよりも、第三者が自らのポジションやキャラクターからイメージされるもの、表現したいものに素直になってもいい、と考えたからこそ、ある意味では徹底したステレオタイプである本篇への出演を受け入れた。だからこそ、いちおうパートナーの名前はクレジットされているが、彼自身の製作会社マルパソは一歩退いている。
大ヒット作に恵まれ、自身の名前だけで客が呼べるようになったエンタテインメント系の俳優は、その個性を活かした作品に頻繁に出演するようになる。監督として、しっかりと地歩を築き上げたからこそ、遅ればせながら、そういう要求に応えてみてもいい、と考えた結果がこの作品なのかも知れない。だから、本篇には彼の映画製作者としての作家性には乏しいが、俳優としての魅力がシンプルに籠められ、いい意味での軽さがある。
関連作品:
『トロイ』
『許されざる者』
『ブラッド・ワーク』
『人生の特等席』
『RED/レッド』
『マイティ・ソー』
『ゴースト・ハウス』

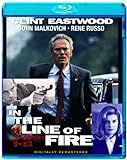
![ザ・シークレット・サービス [Blu-ray] ザ・シークレット・サービス [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51RMZOe6GoL._SL160_.jpg)

コメント