ジョン・ディクスン・カーの影響を強く受けた作品群を著し続けるポール・アルテによる《オーウェン・バーンズ》シリーズ、長篇第8作となる2024年作品。邦訳としては6作目にあたる。
1924年、イギリスの小村バックワースに隠棲する資産家のマチュー・リチャーズの前に、地元で語り継がれる怪異《白い女》が出没する。前々から暮らす次女夫妻と、失踪していた夫と久々に再会し里帰りした長女、そしてふたりの娘よりも年若いマチューの後妻の前に《白い女》はたびたび出没、遂に死者までが出てしまう。人伝に調査を頼まれた、美術評論家にしてアマチュアの探偵オーウェン・バーンズは、この不可思議な出来事を如何にして解き明かすか。
あからさまなまでにカーにオマージュを捧げた《ツイスト博士》シリーズにて日本でも紹介されたが、その後、この《オーウェン・バーンズ》を主な探偵役として作品を書き続けているようだ。その辺の事情も含め、《オーウェン・バーンズ》シリーズについて解説した、飯城勇三による30ページを超える評論が巻末に収録されているので、初心者にもお勧め――と言いたいところだが、ネタばらしを控えつつ、随所で構造には触れてしまっているので、他の作品もまっさらな気持ちで読みたい、という方は、巻末の解説のみ、他の作品も読み終えたうえで接するのが吉だろう。
肝心の本篇は、設定と導入こそ往年のカーを思わせるものだが、物語が始まると、家族のドラマや舞台となる小村独特の事情が絡みあうドラマの趣で、《白い女》が出没するくだり以外はむしろ、危うさを孕んだ人間関係で物語を牽引している。
実際、そこまで複雑怪奇な謎はない――というか、犯罪としては弱い、という程度でしか異変が生じないので、事件が起きた際に行われる検証が精緻ではない、はっきり言ってしまえば雑なので、様々な疑問、解釈の余地を留めたまま進んでいくから、いわゆる密室殺人や、事件当時に犯行可能な人物がいない、といった、手段もそれが可能な人間もいないような、輪郭のくっきりとした謎が浮かび上がってこない。その感覚がもどかしくて、なかなか読み進められない、という人はあるかも知れない。
しかし、ある意味では当然の成り行きである“隔靴掻痒”のイメージのまま、人間関係の微妙な緊張で繋がれていた物語は、突如として意外な惨劇が起きたあたりから雰囲気が変わっていく。それでもなお、どこか本質に届かないようなもどかしさは続くのだが、緊張感はいっそう強まっていく。
一方で、探偵役であるオーウェン・バーンズが、妙に思わせぶりな言動をしたり、特定の人物に忖度するかのような振る舞いを繰り返すことで、また奇妙な感覚を生み出しているのがユニークである。最後まで読んでみれば、物語として、何よりオーウェン・バーンズという人物の物語における機能として、当然の成り行きであったのが解る――この辺は、巻末にある飯城勇三の解説があることも大いに助けになっているが。
クライマックスで謎解きが行われると、いっそシンプルすぎる決着にいささか呆気に取られるが、そこに読者が軽々と歩いて行けないような仕掛けが巧妙で、作品としての計算の高さが窺える。ただ、これを綺麗な決着と捉えるか、はだいぶ好みが割れるのではなかろうか。
解説にもあるとおり、決して往年の本格推理へのオマージュという表現では片付けられない趣向やひねりが組み込まれた、巧妙な作品である――が、それがすべての読者に響くか、はちょっと保証しづらい。
|
![ポール・アルテ/平岡敦[訳]『白い女の謎』(Amazon.co.jp商品ページにリンク) ポール・アルテ/平岡敦[訳]『白い女の謎』(Amazon.co.jp商品ページにリンク)](https://m.media-amazon.com/images/I/815wD3mNAKL._SL1500_.jpg)
 book
book

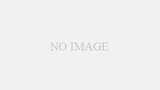
コメント