原題:“Bring Me the Head of Alfredo Garcia” / 監督、原案&脚本:サム・ペキンパー / 原案:フランク・コワルスキー / 脚本&製作補:ゴードン・ドーソン / 製作:マーティン・ボーム / 製作総指揮:ヘルムート・ダンティーネ / 撮影監督:アレックス・フィリップスJr. / 美術:アウグスティン・アイチュアート / 編集:デニス・E・ドーラン、セルジオ・オルテガ、ロッブ・ロバーツ / キャスティング:クラウディア・ベッカー / 音楽:ジェリー・フィールディング / 出演:ウォーレン・オーツ、イゼラ・ヴェガ、ギグ・ヤング、ロバート・ウェッバー、エミリオ・フェルナンデス、クリス・クリストファーソン、ヘルムート・ダンティーネ / 配給:UA / 映像ソフト発売元:20世紀フォックス ホーム エンターテイメント
1975年アメリカ作品 / 上映時間:1時間52分 / 日本語字幕:高瀬鎮夫
1975年7月12日日本公開
2007年8月25日映像ソフト日本最新盤発売 [DVD Video:amazon]
DVDにて初見(2010/11/26)
[粗筋]
ピアニスト兼バーテンダーであるベニー(ウォーレン・オーツ)が勤める酒場に、ある日ふたりの男がやって来て、アルフレッド・ガルシアという男の所在を訪ねた。友人、と言いながら「生死に関わらず」と嘯く男たちの様子に、ベニーは金の匂いを嗅ぎつける。
かつて店の常連であったガルシアは、実はベニーの恋人エリータ(イゼラ・ヴェガ)と密かに関係を持っていた。ベニーが彼女を問い詰めると、ガルシアはつい先日、酔っ払った挙句に事故を起こして死んだばかりだという。
ベニーはガルシアを捜している当事者のもとを訪れ、その話をするつもりだったが、相手は「死んでいても構わないが、その証拠が必要だ」と言った。持ってくる、というベニーに、提示された期限は4日間。それを過ぎれば、命がないと思え、と脅された。
だが、無事に証拠を渡すことが出来れば、1万ドルの報酬が得られる。ベニーはエリータの案内で、ガルシアの墓に向かった。墓を掘り起こし、ガルシアの首を切断して持ち帰るために。
[感想]
実は本篇、リメイクの話が浮上していたことがあった。個人的にお気に入りの俳優ベニチオ・デル・トロが主演する、と言われていたため、完成を心待ちにしていたのだが、どうやらハリウッドにありがちの成り行きで、かなり喧伝されつつも結局は立ち消えとなったらしい――そう思っていると突然復活して、いつの間にか完成品が日本に届いたりするのだが、まあ期待しない方が無難だろう。
出来れば予断抜きでリメイク版を鑑賞したい、と思っていたので、興味を惹かれつつも長いことオリジナルである本篇を鑑賞せずにいたのだが、ここ最近、古い名作を観るのがすっかり楽しみになってしまったことと、評判を聞く限りサム・ペキンパー監督の作る映画はいずれも私の好みのど真ん中に突き刺さっているように感じられたので、リメイクを待つよりは、とようやく借りてきて鑑賞した次第である。
……期待通りであった。心震える、逸品である。
前半は、暴力の影をちらつかせながらも、どちらかと言えば悠長に話は進む。4日を過ぎれば命はない、と脅されながらも、恋人を連れたベニーの道行きは暢気で、一見したところ、自らの置かれた状況を認識していないかのように映る。だが、決して直接口にしない感情を、台詞のニュアンスや表情で滲ませており、画面には終始哀切な空気が漂っている。旅の途中、恋人エリータに愛を囁き、輝かしい未来を語る姿は、ラヴシーンの情感を表現しながらも、異様なやるせなさを湛えている。暴力を直接描かずとも、そこに潜む死の影を匂わせることで、常に命のやり取りを余儀なくされている切実さを描き、ドラマに驚異的な奥行きを齎している。
中盤以降の、予測しづらく、感情を激しく揺さぶる展開も出色だ。遺体を掘り起こして首を切る、というベニーの意図を知って驚き、ギリギリまでささやかな抵抗を試みるエリータの身に降りかかる悲劇が、命の危険を自覚しながらもどこか楽天的だったベニーの振る舞いを一変させる。エリータの身を襲った災厄も特殊なら、その後の事態の推移も一風変わっている。もともと死んでいた男を巡って繰り広げられる虚しい命のやり取りが、最終的にベニーをより強烈な激情に駆り立てるわけだが、これほど意外性に富み、しかしドラマとして必然性のある暴力描写はそうそうお目にかかれない。このくだりのあと、一度自宅に舞い戻ったベニーが、道化めいた振る舞いを見せたあとで、遂に物語は壮絶かつ熱いクライマックスを迎える。
決してベニーも善人ではない。だが、無意味な殺し合いを経て示す押し殺した憤りは、否応なしに観る側を共感させ、最後の行動で胸を熱くさせてしまう。決して自己陶酔的な台詞はなく、どちらかと言えば肝心の場面では敢えて踏み込まない、過剰に描き込まない演出をしているのに――いや、だからこそ、その惨めな生き様が清々しく、格好良く映る。
こうして語れば見事なまでの“男のドラマ”なのだが、しかし一方で印象に残るのは物語を大きく動かすふたりの女だ。エリータという女性は終始ベニーのモチベーションとして大きな存在となっているが、要所要所で示す表情や振る舞いに逞しさと哀しさとを閃かせ、出番の最後あたりに見せた姿が忘れがたい。また、物語のそもそもの発端となった、ガルシアによって妊娠させられた女性が、最後に受け身の仮面をかなぐり捨てる場面も秀逸だ。このふたりの儚くもしたたかな姿が、薄汚れた物語に不思議な気高さを齎している。
人の倫から外れながらも、命の極限で矜持を示す本篇に漂うのは、硬質の詩情だ。激しい暴力描写に常識派は眉をひそめるかも知れないが、しかしそこから目を逸らしていないからこそ、本篇は空虚でありながらも美しい。期待していた通り、『誘拐犯』や『メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬』といった映画を愛する私にとって、惚れ込まずにはいられない傑作であった。
……実際に観たあとだと、これ以上のものを作るのは決して容易ではない、という意見が非常に頷ける。だが、それでもなお、ベニチオ・デル・トロが演じるベニーが観てみたい、と私は思う。演出次第ではあるが、デル・トロならばこの泥臭さと哀愁を漂わせた男を見事に体現することが出来ると思うのだけど……。
関連作品:
『荒野の用心棒』
『誘拐犯』

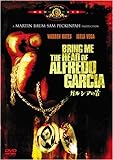
![ガルシアの首 [DVD] ガルシアの首 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51KqS0twj3L._SL160_.jpg)

コメント