原題:“Spider-Man : Into the Spider-Verse” / 監督:ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン / 原案:フィル・ロード / 脚本:フィル・ロード、ロドニー・ロスマン / 製作:アヴィ・アラド、フィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカル、クリスティーナ・スタインバーグ / 製作総指揮:ウィル・アレグラ、ブライアン・マイケル・ベンディス、スタン・リー / 視覚効果スーパーヴァイザー:ダニー・ディミアン / プロダクション・デザイナー:ジャスティン・K・トンプソン / 編集:ロバート・フィッシャー・Jr. / アートディレクター:ディーン・ゴードン、パトリック・オキーフ / キャラクターデザイナー:シユン・キム / ストーリー統括:ポール・ワトリング / レイアウト統括:デイヴ・モアヘッド、リッチ・ターナー、ジェイムズ・ウィリアムズ / キャラクターアニメーション統括:ジョシュ・ベヴァリッジ / キャスティング:メアリー・ヒダルゴ / 音楽スーパーヴァイザー:キア・リーマン / 音楽:ダニエル・ペンバートン / 声の出演:シャメイク・ムーア、ジェイク・ジョンソン、ヘイリー・スタインフェルド、リリー・トムソン、リーヴ・シュレイバー、ジョン・ムレイニー、キミコ・グレン、ニコラス・ケイジ / 日本語吹替版声の出演:小野賢章、宮野真守、悠木碧、沢海陽子、玄田哲章、吉野裕行、高橋李依、大塚明夫 / 配給:Sony Pictures Entertanment
2018年アメリカ作品 / 上映時間:1時間57分 / 日本語字幕:佐藤恵子
2019年3月1日日本公開
公式サイト : http://www.spider-verse.jp/
TOHOシネマズ上野にて初見(2019/3/25)
[粗筋]
ピーター・パーカー(ジェイク・ジョンソン/宮野真守)はこの世でただひとりのスパイダーマンだった。赤と青で彩られたスーツを纏い、壁や天井を自在に歩き、スパイダーウェブを駆使して街を縦横に飛び回り、悪党たちと戦っている。コミックになり、カバーアルバムのリリースまで実現して、彼はいまやニューヨークの英雄だった――そのときが来るまでは。
マイルス・モラレス(シャメイク・ムーア/小野賢章)は警察官の父ジェファーソン・デイヴィス(ブライアン・タイリー・ヘンリー/乃村健次)と医師のリオ・モラレス(ルナ・ローベン・ヴェレス/小島幸子)のあいだに生まれ、ブルックリンで育った。父はマイルスの知力に可能性を見出し、彼を最先端の教育を施すヴィジョン高校に編入させるが、エリートばかりの環境にどうしても馴染めない。悩んだとき、マイルスはアーロン叔父さん(マハーシャラ・アリ/稲田徹)のもとに駆け込んだ。父のように犯罪とすっぱり縁を絶つことが出来ず、そのために父とは疎遠になっているが、自分の芸術への憧れを理解してくれる叔父さんは、マイルスの心の支えだった。
学校での緊張感や両親の期待に耐えかねて訪ねてきたマイルスを、アーロン叔父さんは地下道へと連れてきてくれた。剥き出しの壁に、マイルスは想いの丈を籠めて絵を描いた。マイルスが、あのクモに噛みつかれたのは、そのときのことだった。
その晩、マイルスは異様な身体の熱と、奇妙な感覚に悩まされる。しかも、掌で触れたものが簡単に剥がれなくなった。恐る恐る登校した矢先に、自分同様転校してきたばかりのワンダ(ヘイリー・スタインフェルド/悠木碧)の髪に触ってしまい、彼女の髪を剃る事態に。
動揺したマイルスはふたたびアーロン叔父さんを訪ねるが、仕事のために彼は家を空けていた。マイルスは昨晩、訪れた地下道にふたたび赴き――そこで、運命的な出来事と遭遇する――
[感想]
近年、アメコミ原作のヒーロー映画が隆盛となっている。『アベンジャーズ』シリーズを軸とするマーヴェルの作品群は軒並み記録的な興収を上げ、当初は後塵を拝していたDCも『ワンダーウーマン』の成功を皮切りに急速に追い上げ始めた。恐らくは本篇は、そういう状況だからこそ生まれ得た傑作と言える。
CG主体のアニメなのだが、最初から妙な違和感を覚えるはずである。CG映画特有の滑らかな描画が少なく、どこかギクシャクした印象を受けるはずだ。
その意味が理解できるのは、粗筋で記した出来事のあと、他の“スパイディ”たちが登場してからだ。マイルスが知っているよりも年老いたピーター・パーカーが現れ、ピーターではなくその幼馴染みの少女が蜘蛛の力を得た世界からもやって来る。更にはモノクロの世界、少し古い漫画の世界、更にはよりナンセンスな漫画の世界から現れたスパイダーマンたちが登場する。特に後者の3名は、表現する方法自体が異なっている世界から来ているため、デザインの理念そのものが異なっている、というわけである。
それだけなら表現上の趣向、という程度で終わるが、本篇はそこで終わらない。“カオス”と形容したくなるほどに多彩なキャラクターと表現を織り込みながら、彼らとの交流によってマイルスが正しく“ヒーロー”として覚醒するさまを追う、いわゆる“ヒーロー誕生物語”として成立させているのだ。
力を得たからといって、誰もが即、ヒーローになるわけではない。ヒーローに憧れていても、高い志があったとしても、順調にヒーローになることなどあり得ない。そのためには己の力の使い方を知り、覚悟を決める必要がある。“スパイダーマン”のシリーズはそもそも、このヒーローとしての自覚に目醒めるプロセスが明確だ。変質した蜘蛛に噛まれることで力を得、人生が一変する。その力に溺れて増長し、何らかの挫折を味わう。そして、本当に求められた瞬間に自らの使命を悟り、ようやくヒーローとして覚醒する。
本篇は、異世界から現れた“スパイダーマン”たちの言動によって、そうしたスパイダーマンの基本とも言える通過儀礼をパロディ化しつつも堅実に再生する。近い道を辿っているだけにどこか滑稽だが、明白であるがゆえに紆余曲折が長く感じられ、そのぶんだけマイルスが目醒めた瞬間のカタルシスが強烈になっている。
パロディ化、という意味でいちばん解り易いのは、マイルスと同じ次元のピーター・パーカーよりも年老いた、もうひとりのピーター・パーカーのエピソードだろう。“スパイダーマン”には一貫して、ヒーローものでありながら青春物語である、という性質があるが、それ故にあまり触れられない、ヒーローがヒーローとしての責務を果たしながら年老いたらどうなるのか? ということを、悲哀の籠もったパロディのかたちでシミュレーションしている。笑える一方で、自覚もなく理解者もいないままヒーローを続けることの重責をまざまざと見せつけられるようで、実に切ない。
別々の次元で“スパイダーマン”として活躍する彼らは、性別、本来の世界の科学水準、戦い方に至るまで大きく異なりながら、しかしヒーローとして独り立ちするまで、そしてそのなかで諦めたもの、失ったものに共通点を持っている。だからこそ成立する共感と理解が、同じ道を辿がろうとしているマイルスを、観客にとっても解り易く導いている。
そして、この複数の、同じような通過儀礼を経てヒーローとなった者が存在する、という世界観と語り口は、“どこにでもヒーローはいる”、“誰でもヒーローになれる”という、マーヴェル作品が持つテーマを強い光で照らすものでもある。
彼らは確かに一般人とは異なる能力を身に付けている。蜘蛛の力もさることながら、スパイダーマン達は共通してみな科学者の顔も併せ持っており、それもまた彼らをヒーロー、とりわけ“スパイダーマン”たらしめているのは確かだ。だが、力や技術を持っていようと、それを正しく行使する意志、覚悟がなければヒーローたり得ない。翻って、力を適切に使い、誰かを助けよう、誰かの力になろう、とするひとこそがヒーローだ、とも訴えている。
本篇はこの、マーヴェル作品に通底するテーマを、これまでになく力強く照射し、明快に描き出す。だからこそカタルシスもまた明快であり、ヒーローになりたい想いがある、ヒーローに憧れを持つ者の心を震わせずにおかない。
また“スパイダーマン”は、他のヒーローたちと共演する“マーヴェル・シネマティック・ユニヴァース”の一員として活躍する場合を除けば、本質的に孤独でもある。そんな彼らにとって、例え別世界であっても、同じ志を持つ者がいる、という事実は間違いなく救いとなる。そして、その想い一つさえあれば、誰でもヒーローになり得る、という確信をも与える。
本篇はいささかカオスなほどヒーローが溢れかえっているが、しかしその誰もが最初からヒーローだったわけではないことを窺わせる。言い換えれば、誰もが自らの才能を活かすことでヒーローになり得る可能性がある、と示している。そう気づかされるからこそ、クライマックスでのマイルスの“覚醒”に心躍らされてしまう。
本篇はヒーロー映画の優れた自己模倣であり、だからこそ成立した、最高のヒーロー映画なのだ。
関連作品:
『スパイダーマン』/『スパイダーマン2』/『スパイダーマン3』/『アメイジング・スパイダーマン』/『アメイジング・スパイダーマン2』
『ジュラシック・ワールド』/『トゥルー・グリット』/『ピンクパンサー2』/『ジゴロ・イン・ニューヨーク』/『犬ヶ島』/『ゴーストライダー2』
『聲の形』/『プリキュアスーパースターズ!』/『はいからさんが通る 後編 ~花の東京大ロマン~』/『キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと! 想い出のミルフィーユ!』/『シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>』/『夜は短し歩けよ乙女』/『イノセンス』
『THE ONE』/『テッセラクト』/『ハウンター』/『プリキュアオールスターズ New Stage/みらいのともだち』

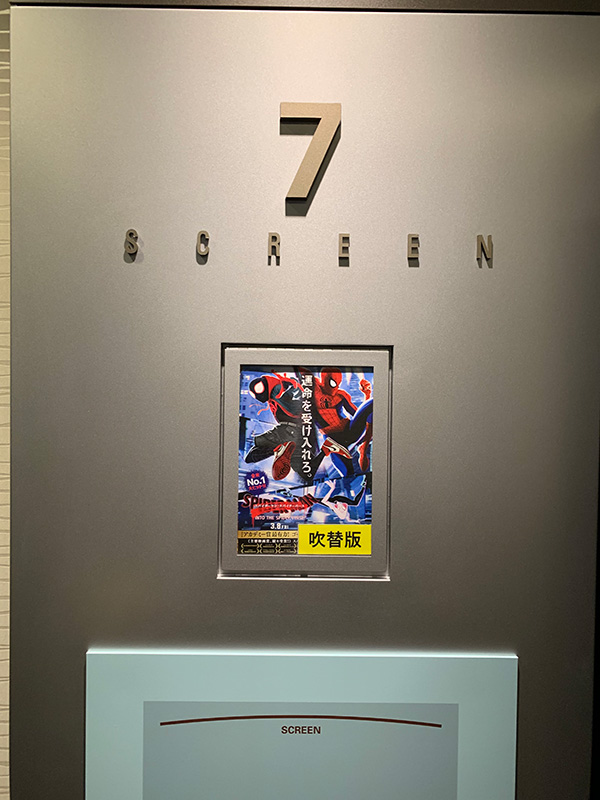

コメント