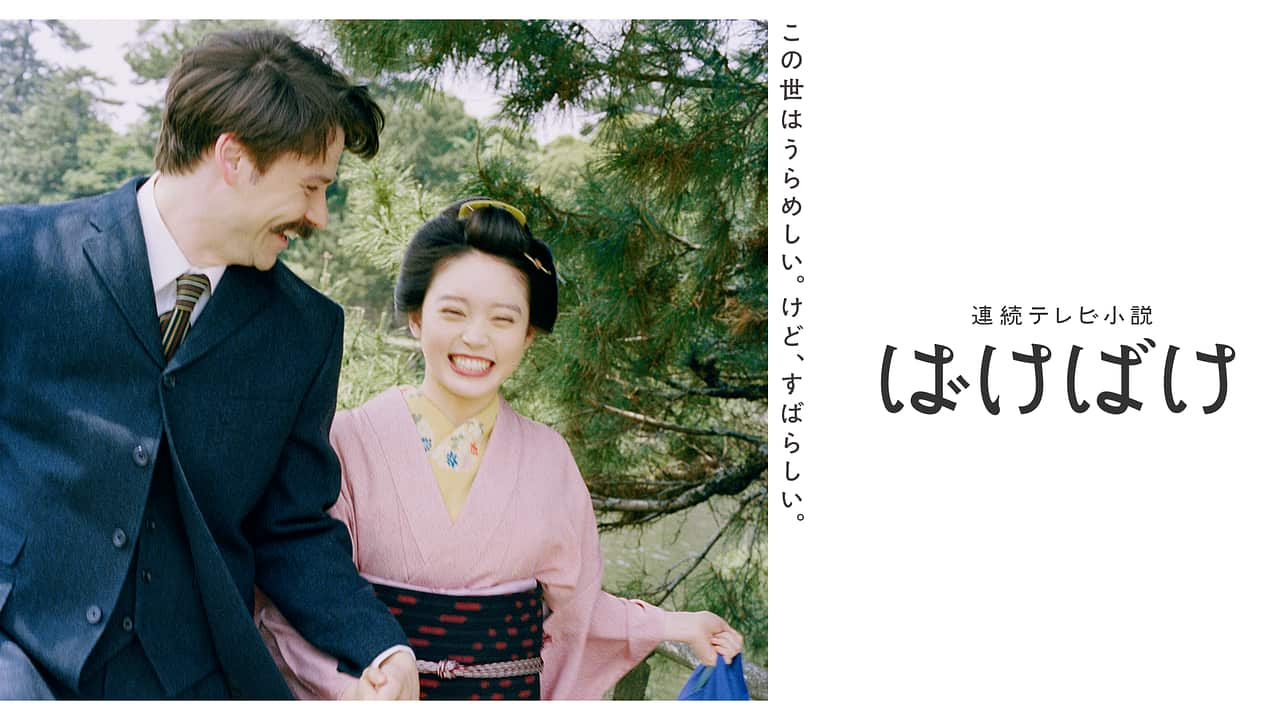
……結局毎日書くんか、と思われてますよね。私も思ってます。でも触れたくなっちゃったから仕方ない。
司之介お父様の商売も気になりますが、まあそこは置いといて、問題は第三回終盤のお父様の台詞です。
「松江はこの大橋川を挟んで我々が住むお城側は格式の高い武家の町、川の向こうは商人と貧しい者の町と分かれちょる」
松江城側から大橋を越えたあたりは“白潟地区”と呼ばれ、商家や寺院が多い。私はちょうど今年冬、松江観光大使にして遣島使の声優・茶風林さんのトークイベントが開催されたので、付近をうろついていましたが、お堀に沿って区画整理された松江城付近と異なり、路地の入り組んだところでした。一方で、現在もJR松江駅があるなど、松江市の商業の拠点でもあります――最近は空洞化も進んで問題となっているようですが。
しかしその実、白潟地区は松江城よりも先に存在し、南北朝時代には既に港町があった。日本海と宍道湖との交易拠点として、大橋川にあった砂州で発展した土地で、ここに経済拠点があるから、松江城が築かれた、という背景がある。湿地帯だったため、城を中心に堀を巡らせ、宍道湖や大橋川と結んで排水したことが、“水の都”とも言われる現在の松江の風景を生み出している。お父様は武士の矜恃ゆえに蔑んだ言い方をしてましたが、歴史を辿れば、決して軽視していい土地ではないのです。
だから……さすがにこれくらいは言ってもいいと思うけど、お父様は今日の第三回ぜんぶ使って、フラグ立てていたようなものだと思う。トキの苦難はこれからです。
参考文献
NHK「ブラタモリ」制作班[監修]『ブラタモリ4 松江 出雲 軽井沢 博多・福岡』(扶桑社)
『シリーズ しまねの遺跡 発掘調査パンフレット13 松江城下町遺跡 白潟地区-中世の港町から近世城下町へ-』図録(島根県教育長埋蔵文化財調査センター)


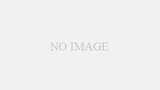
コメント