原題:“First Man” / 原作:ジェイムズ・R・ハンセン / 監督:デイミアン・チャゼル / 脚本:ジョシュ・シンガー / 製作:マーティ・ボウエン、デイミアン・チャゼル、ウィック・ゴッドフレイ、アイザック・クラウスナー / 製作総指揮:アダム・マリムス、ジョシュ・シンガー、スティーヴン・スピルバーグ / 撮影監督:リヌス・サンドグレン / プロダクション・デザイナー:ネイサン・クロウリー / 編集:トム・クロス / 衣装:メアリー・ゾフレス / キャスティング:フランシーヌ・メイスラー / 音楽:ジャスティン・ハーウィッツ / 出演:ライアン・ゴズリング、クレア・フォイ、ジェイソン・クラーク、カイル・チャンドラー、コーリイ・ストール、パトリック・フュジット、クリストファー・アボット、キアラン・ハインズ、オリヴィア・ハミルトン、パブロ・シュライバー / テンプル・ヒル製作 / 配給:東宝東和
2018年アメリカ作品 / 上映時間:2時間21分 / 日本語字幕:松浦美奈 / 字幕監修:毛利衛
2019年2月8日日本公開
公式サイト : http://firstman.jp/
TOHOシネマズ上野にて初見(2019/3/7)
[粗筋]
ジョン・F・ケネディ大統領の演説を契機に、アメリカとソビエト連邦は本格的な宇宙開発競争に突入する。
民間企業で飛行機のテストパイロットを務めていたニール・アームストロング(ライアン・ゴズリング)のもとにも、宇宙開発計画の一部である“ジェミニ計画”の話は届いていた。しかし当時のアームストロングにとって最も優先されていたのは、長女カレンの治療だった。幼くして重篤な病に冒された彼女を救うため、先進的な研究が行われているカナダへの移住すら検討していた。
しかし、カレンはほどなく小さな命を散らした。衝撃も冷めやらぬまま、職に復帰した彼のデスクには、“ジェミニ計画”のパンフレットが置かれていた。
首尾よく選考を通ったアームストロングは、第三子を身籠もった妻のジャネット(クレア・フォイ)と長男を伴い、ヒューストンに転居する。月探査を目指す“アポロ計画”への布石となる“ジェミニ計画”のパイロット候補として、それまで誰も経験したことのない実験や訓練に取り組んでいく。
自分と同様に民間出身のエリオット・シー(パトリック・フュジット)、家が向かいで家族ぐるみの付き合いをするようになったエド・ホワイト(ジェイソン・クラーク)など、辛苦を共にした仲間との絆は深まっていったが、ジェミニ計画遂行への道程は遠かった。そうこうしているうちにソ連が宇宙空間での船外活動に成功した、という報が届き、既にかなり後れを取っていたアメリカは、宇宙開発の分野で更にソ連の後塵を拝してしまう。
1699年、ジェミニ計画はようやく、アポロ計画への里程標である、宇宙空間でのドッキング実験を遂行する段階に入った。無人の目標機アジェナとドッキングする有人機ジェミニ8号の船長に選ばれたのは、アームストロングであった。
だがその決定が告げられて間もなく、選考に漏れたエリオットが、次の機会を得ることなく、訓練機の事故により亡き人となる。自分たちが危険な任務に携わっていることを再認識したアームストロングは、この大事なドッキング実験で、まさに死の縁を覗き見ることとなった――
[感想]
デビュー作『セッション』でいきなり賞レースを騒然とさせ、続く『ラ・ラ・ランド』で早くもアカデミー賞監督部門賞を受賞したデイミアン・チャゼル監督の長篇3作目は、これまでと趣を変え、実話ベース、ドキュメンタリー的な撮影手法を用いている。
だが、1作目から濃厚に見せていた、映画に対する造詣の深さ、拘りは本篇にもハッキリと窺える。
撮りかたそのものは、21世紀に入ってから多くなった、手持ちカメラを主体としたドキュメンタリータッチを指向している。この手法は物語にリアリティを付与するために用いられることが多く、本篇でもその意図は窺えるが、それ以上に狙っているのは、観客に“人類初の月面探査”を疑似体験させることのほうだ。
それ故に本篇は、異常なほど登場人物の近くにカメラを据え、彼らの表情と共に、その目に映るもの、感じる轟音や振動などを捉えている。その姿勢は実験機の段階から一貫しており、観ている側はその危険性、宇宙飛行士たちが味わう恐怖も疑似体験することとなる――映画であるが故に、本当に不愉快にならない程度に留めてはいるが、宇宙飛行士たちが抱く感情、並々ならぬ覚悟の一端は確実に伝えている。
もちろん、この趣向のいちばんの狙いはクライマックス、誰もが知る人類初の月面着陸を体感させることだ。そのため、本篇ではドキュメンタリー的な至近距離からの撮影のみならず、アームストロング自身の視点からの描写も交えている。リアリティという意味では諸刃の剣になりかねない手法だが、ここぞ、というところで用いているので、違和感をもたらさない。
本篇ではCGに極力頼ることなく、昔ながらの“特撮”の手法を用いている。たとえば上昇するロケットや宇宙空間の森閑として済んだ空間、そして間近から眺める月の表面などは、かつての書き割りの代わりにプロジェクターで投影した映像やミニチュアを駆使し、可能な限りカメラで捉えているという。ものによっては宇宙飛行士を演じる俳優自身が観客とほぼ同じヴィジュアルを眼にしているわけで、だから彼らの演技に嘘くささも違和感も覚えにくい。本篇は徹底して、観客がその感覚をリアルに味わえるよう配慮して作られているのだ。
ドラマとしての組み立てにもその配慮は窺える。人類初の大事業は当時から注目を集め、賞賛も誹謗中傷も囂しかったが、本篇ではそうした点を過剰に採り上げることはしていない。本篇はむしろ、アームストロングの家庭人としての側面に焦点を当てている。
意外だったのは、アームストロングが月面探査の計画に加わるようになったきっかけのひとつに愛娘の死があった、という描写だ。本篇はアームストロングが生前、唯一取材を許したライターによるルポルタージュに基づいており、フィクション的な潤色や誇張があるにしても、その動機に娘の存在があったことは事実らしい。生前、アームストロングはあまり多くを語る人物ではなかったようで、本篇はそういう人柄もきちんと再現しながら、家族との関係性を描き、その内面を垣間見せる。
そうして浮かび上がるのは、人類にとって意義のある計画に携わっている、という自負以上に、まるで巡礼めいたアームストロングの姿勢だ。やもすると家族に対して冷淡に映るその態度にも、罪悪感や贖罪の意識がちらついている。さながらその代償として、いつ命を落としても不思議ではない計画に臨んでいたかのようだ。
そうした家族との距離感を織り込んでいるから、待つ側であった妻の心情も伝わり、それらが凝縮されたクライマックス寸前の家族の会話が痛いくらいに沁みる。その先にある偉業に、物見遊山的な好奇心や、軽薄な功名心とは違ったものが見えてくる。
月に足を下ろしたその瞬間よりも、アームストロングが月で試みたある行動や、帰還したあとのほうが本篇は心を震わされるはずだ。人類初の偉業、という側面ではなく、その人間性や感情に寄り添ったからこそ生まれる感動なのである。
こういうことをきっちり狙って形にする、というのは言うほど簡単ではない。やはりこの監督、ただ者ではない。
関連作品:
『マネー・ショート 華麗なる大逆転』/『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』/『キャロル』/『ボーン・レガシー』/『ゴーン・ガール』/『沈黙-サイレンス-(2016)』
『ライトスタッフ』/『カプリコン・1』/『ウォッチメン』/『アルマズ・プロジェクト』/『アポロ18』/『月に囚われた男』/『地球、最後の男』/『ゼロ・グラビティ』/『インターステラー』/『オデッセイ』

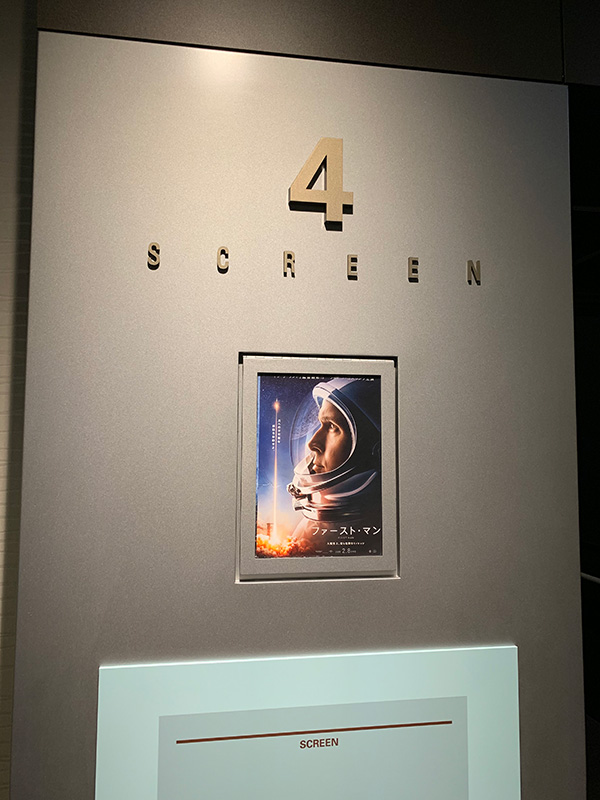
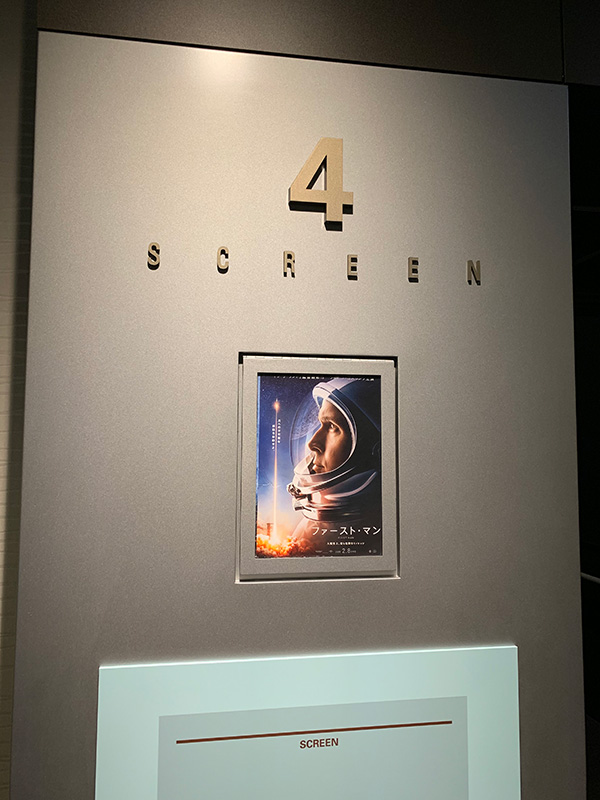

コメント