Webの小説投稿サイト《カクヨム》で発表されるや、多くのホラー好きを唸らせた長篇の文庫版。オカルト雑誌や一般誌、ネット上の投稿に散見する、どこか共通点のある奇妙な話。それらはすべて、近畿地方のある場所を示していた。別冊Qの副編集長を務める小澤は、旧知のライター・瀬野が提示したこの不気味な謎を彼女と共に追ううちに、ある結末に辿り着く――
“文庫版”と敢えて強調してあるのは、内容に手が加えられた、という点を明示する意図からのようだ。珍しいことに、文庫裏の粗筋にまで特記されているほどだったので、映画版を鑑賞する前の予習・復習がてら読むことにした。
確かに、違う。思っていた以上に、余韻が変わっている。
多くの雑誌記事や、記事にならなかったインタビュー、関連すると思われる文章をちりばめて、“近畿地方のある場所”に秘められたものを探り出そうとする、という骨格は変えていないし、そうした記事も内容的にはほとんど単行本版と同一のはずである。
ただ、『近畿地方のある場所について』と題された、記事を抽出し考察する取材者たち本人の記述に大きく違いがある。そしてこの違いが、のちのち大きな意味を持つようになる。
Web版や単行本版を読んだ上で、“内容が異なる”という本書を楽しみにしている方のために、どう違うのか、あまり詳しく説明することは避けたいが、この加筆改稿が導く終盤の変化はかなり大きい。本当に、終盤で読者を襲う感情も、読み終わったあとの余韻までも違ってくる。
憶測するならそれは、オリジナル版によって評価された著者が、そこから生まれた縁により、近しい志向のクリエイターと触れ、異なる媒体でのホラー表現にも臨むようになって、オリジナル版が最初から備えていた要素を掘り下げることに辿り着いたのではなかろうか。
これも憶測だが、映画化にあたって、フェイク・ドキュメンタリースタイルの先駆者である映画監督・白石晃士が実写版を手懸けることになり、脚本執筆の上でも協力することで、この文庫版の内容も固まっていったのかも知れない。
これを書いている現時点で既に実写映画版を鑑賞したあとだが、実際映画版は単行本版ではなく、メインエピソードの登場人物を追加したこの文庫版と要素が繋がっている。本書に至る改稿が先立ったのか、映画版を製作する上での協議が影響しているのか、私は確認していないが、本篇の人物配置や終盤のドラマ性は、映画版と共鳴しあっているのは間違いない。単行本版だけ読んだうえで映画版を鑑賞しようとしている人は、むしろ先に本書を読んでおくべきかも知れない。
あまりに終盤の印象、余韻が異なるため、人によっては単行本版の方が面白い、より怖かった、と評価することもありそうだ。ただ、テーマを掘り下げ、ことなる恐怖、感動を揺さぶる作品へと昇華したこの文庫版は、書き手としての著者の成長、洗練がはっきりと窺える。
間違いなく令和のホラーブームを象徴する1冊だが、単行本版と比較したときのそうした変化すら象徴的で、たぶん今後もホラーの歴史を語る上で欠かせない作品だろう。
|

 book
book

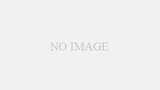
コメント