
TOHOシネマズ上野、スクリーン7入口脇に掲示された『ゴッホ 最期の手紙』チラシ。
原題:“Loving Vincent” / 監督:ドロタ・コビエラ、ヒュー・ウェルチマン / 脚本:ドロタ・コビエラ、ヒュー・ウェルチマン、ヤツェク・デネル / 製作:ヒュー・ウェルチマン、ショーン・ボビット、イヴァン・マクタガード / 製作総指揮:クローディア・ブリュームフーバー、ガード・シェパーズ、イアン・ハッチンソン、シャーロッテ・ウベン、ラウリー・ウベン、エドヴァルト・ノルトナー、デヴィッド・パーフィット / 撮影監督:トリスタン・オリヴァー、ウカシュ・ジャル / 編集:ユスティナ・ヴィエルシンスカ、ドロタ・コピエラ / 音楽:クリント・マンセル / 出演:ロベルト・グラチーク、ダグラス・ブース、ジェローム・フリン、シアーシャ・ローナン、ヘレン・マックロリー、クリス・オダウド、ジョン・セッションズ、エレノア・トムリンソン、エイダン・ターナー、ビル・トーマス、ロビン・ホッジス、ピョートル・パムワ、エザリ・ウカシェヴィチ、ボジェナ・ベルリンスカ=ブリゼック、ジョッシュ・バーデット、ホリー・アール / 配給:PARCO / 映像ソフト日本最新盤発売元:Happinet
2017年ポーランド、イギリス、アメリカ合作 / 上映時間:1時間35分 / 日本語字幕:?
2017年11月4日日本公開
2022年1月14日映像ソフト日本最新盤発売 [DVD Video|Blu-ray Disc]
公式サイト : http://www.gogh-movie.jp/ ※閉鎖済
TOHOシネマズ上野にて初見(2017/11/4)
=
[粗筋]
1891年、フィンセント・ファン・ゴッホ(ロベルト・グラチーク)の死から1年あまりが過ぎた頃、アルマン・ルーラン(ダグラス・ブース)は郵便局長である父ジョゼフ・ルーラン(クリス・オダウド)に命じられて、パリにいるフィンセントの弟テオ(ツェザリ・ウカシェヴィチ)のもとへと向かった。
手紙はゴッホが最期に下宿していた部屋に残され、大家が秘匿していたものである。ゴッホは自らの耳を切断する事件を起こして以来、狂気に取り憑かれた人物として倦厭され、追放の署名運動も起きている。大家もまた署名していて、関わり合いになることを避けた。生前のゴッホと友好な関係を築いていたジョゼフは、その事実を知り、ゴッホの最期の意思を伝えようとしたのである。
乗り気ではなかったアルマンは、飲んだくれて細馬で喧嘩しているところを父に見つかり、改めて命じられ渋々パリへと赴いた。だが、宛先の住所にテオはおらず、隣人の助言を受けて、アルマンは画商のもとを訪れる。画商は、長年支えてきた兄の死をきっかけにテオは著しく衰弱、翌年早々に亡くなったという。画商は、絵を学んで僅か数年で、影響力のある画家になったゴッホは謎であり、しかしパリにおいては兄弟共々“亡霊”のようなものだ、と語る。
アルマンは、画商の話から、フィンセントの最期の手紙は彼の主治医となったポール・ガシェ(ジェローム・フリン)が相応しいのではないか、と考え、ガシェのいるオーヴェールへと向かう。
だが、ガシェは不在だった。フィンセントが逗留したのと同じ宿、同じ部屋を借りたアルマンは、ガシェを待つ間、住民たちにフィンセントについての訊ねて回る。そうして浮かび上がるのは、人によって180度異なるフィンセントの人物像と、その死にまつわる謎であった――
[感想]
どういう映画なのか、知った上で劇場まで脚を運び鑑賞している。しかし、知っていてなお、映像を観たとき度肝を抜かれ――正気の沙汰じゃない、と思った。
実写でいちど撮影したものを、1コマずつトレースし、動きの極めて自然なアニメーションにする“ロトスコープ”という手法じたいは珍しいものではない。日本のアニメーションでもときおり用いられているし、リチャード・リンクレイター監督は『ウェイキング・ライフ』と『スキャナー・ダークリー』で二度にわたって導入、現実と妄想の境にいるような奇妙な感覚を描きだした。デジタル化が進んだ今でも、この手法をベースにした表現は繰り返し試みられている。
だが、この作品は桁が違う。ロトスコープであることは間違いないが、すべてのシーンが一枚の絵画だ。しかも、物語の視点人物となるアルマンがゴッホの手紙を届ける相手を探しているリアルタイムの部分は、まさしくゴッホそのもののタッチで再現されている。ゴッホ自身の作品と構図を活かしたシーンも多く含まれ、本篇そのものがゴッホの作品のような趣を示している。
物語は、既に亡くなった人物の手紙を、1年後に届けるためのアルマンが、その旅の過程で様々な人々の証言からゴッホ晩年の数ヶ月を辿る形で描かれる。その中で常に、ゴッホが本当はどういう人物なのか、何故、不可解な死を遂げたのか、という謎がまとわりついてくるのだ。アルマンの暮らすアルルでは、追放する署名が行われるほど危険視される行動が目立ち、ガシェ医師の家政婦も“邪悪な人間”と評する。しかし、アルマンの父ジョゼフや、逗留していた宿の主人の証言からはむしろ、繊細で優しい人柄が浮かび上がってくる。そして、亡くなる前のフィンセントは一時期の不安定な状態を乗り越え、穏やかな振る舞いをしていたのが窺える。当人も手紙の中で「完全に冷静な状態だ」と説明しているのに、突如として自ら死を選ぶことがあるだろうか。
最初は父の使いの仕事に不満のあったアルマンだが、警察が自殺と断定したことに疑問を抱き始める。そうして次第に、手紙を託す相手と同時に、死の真相を探り出すことにも執着し始める。冒頭で喧嘩沙汰を起こし、中盤でも暴力行為に走ってしまうアルマンは、そんな情緒的不安定さが自身と似ているフィンセントに共感を覚えているように見え、自身も感じている居心地の悪さを正そうとするかのように“真相”を求めるのだ。
調べきれなかったため断言は出来ないが、実際にフィンセントが画題とした郵便局員ジョゼフ・ルーランは実在し、息子もこの交流に関わっていたところまでは確認出来た。彼に限らず、本篇に登場する人物はほとんどがフィンセントの怪画のモデルとなっており、実在している。
そうして、絵の中でしか観ることの出来なかった人々が、絵のままで動き出す、というのも本篇のユニークな魅力だが、興味深いのは、そうした彼らの証言、印象が結びついた先に浮かび上がる推測が、現実のフィンセント・ファン・ゴッホの死の真相としてもかなり的を射ているように思えるのだ。確かに、残されている記録に覚える違和感は、この解釈なら辻褄が合う。エンドロールで提示される情報も、保身からついた嘘が混ざっている、と考えれば、矛盾はしない。
だが、そうして説得力のある解釈を示しつつも、本篇の幕引きはそこに固執していない。むしろ、そこで推測される事実を受け止めた上だからこそ感じられる、フィンセント・ファン・ゴッホという人物の複雑で繊細で、どうしようもなく暖かな心象に触れるような心地がする。彼が残した絵画に感じる拭いきれない寂寥と、その奥にある優しさや暖かみに、より深く浸るかのようだ。
まるでフィンセントの眼差しを再現するかのようだが、忘れてはならないのは、本篇がフィンセントの死後の出来事として綴られていることだ。如何に彼の作品をモチーフとして吸収しても、それは解釈のひとつを、フィンセントの画風に寄せて再構築したに過ぎない。だが、その自覚と節度こそが、本篇をフィンセント・ファン・ゴッホという不世出の画家への敬意を強く籠めたオマージュとして成立させている。
映画としても優秀だが、現代におけるフィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品を解釈して生み出された芸術として、残されるべき名作であると思う。
関連作品:
『ジュピター』/『グランド・ブダペスト・ホテル』/『レディ・バード』/『007/スカイフォール』/『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』/『フィルス』/『ジャックと天空の巨人』
『ウェイキング・ライフ』/『スキャナー・ダークリー』/『戦場でワルツを』
『ポロック 二人だけのアトリエ』


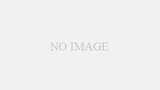
コメント