紆余曲折を経て、ようやく松江怪談談義です。……と言いつつ、到着して最初にするのはお買い物なわけですが。きょう初出しの木原浩勝さんの便利アイテムとか、ただいま大量に刊行され続けている関連書籍から2冊選んで購入。ちなみに、物販の向こうで関係者が次の新刊のチェックを実施してたらしい。大変だ。更に口車に乗せられて、ビアへるんの怪談テーマのアルコールを3種と、そのラベルを用いたグラスのセットを購入してしまった……明日、飛行機なんだけど、どうやって割らずに持ち帰ろうかしら。
そうこうしているうちに開演時間へ。小泉八雲・セツから四代目にあたる民俗学者の小泉凡氏と、怪異蒐集家の木原浩勝氏が登壇して、本篇スタートです。
なお、このあとの文章には、もしかしたら『ばけばけ』でこのあと触れるかも知れない要素がたくさんありそうなので、なるべくまっさらな状態で鑑賞したい方は回れ右をお願いします。いちおう少し改行を挟んで、本題に入ります。
なお、基本的にはあまり内容に添って整理せず、現地でお二人が話した順番に添って記してますので、あちこち話題が前後しますがご容赦を。
松江怪談談義10話にして、合わせたかのように小泉セツをモデルにした『ばけばけ』が始まった以上、今年のテーマは小泉セツ以外に有り得ません。直前に催された、松野司之介役・岡部たかしと凡氏が立ち会っての初回ライブビューイングの際に撮影したという、例のわら人形を持って笑う凡氏がおかしかった。
木原氏いわく、そもそもNHKで怪談がテーマのドラマが始まるのが画期的だという。だいぶ前に怪談をめぐるドキュメンタリーを木原氏が提案した際は拒まれ、のちに海外がメインとなって製作する形で実現した際も、日本だけが『異界百物語』というメインタイトルに、“Jホラーの源流”というサブタイトルがつけられる、そのくらいの空気感だったそう。
松江で撮影が進行しているため、もちろん凡氏は出演者とも面識がある。主演二人を賞賛されてました。高石あかりは前向きさと自然体のスタンスがセツに通じ、トミー・バストウはもともと日本好きで日本語が堪能、そのうえ今回、八雲をもとにした人物を演じるため、八雲=ハーンの著述をアメリカ時代から順番に通読したという。こんな記事も書いていた、と凡氏が見せられた記事に読んだ覚えがなく、現在、凡氏よりも八雲の文章をよく記憶してるかも知れないとか。
“ばけばけ”というタイトルの由来に加え、ドラマでもベースとなる八雲とセツの共鳴にも言及。ふたりとも貧しい暮らしを経験し、いずれも離婚を経験している。何より、二人とも物語が好きで、身辺に語り部がいた。ハーンは乳母を筆頭に、各時代にその土地の物語を語ってくれる人物がいた。ニューオーリンズの当時にはヴードゥー教について聞いており、実はいわゆる“ゾンビ”という存在を日本に広まるきっかけも八雲だったらしい。カリブ海に浮かぶフランス領地マルティニーク島は特にハーンに強い影響を及ぼし、セツもさんざん聞かされたその名を記憶していたとか。
話はドラマにおける《松野トキ》という主人公の名前の出所について。これが小泉八雲がセツに宛てて書いた手紙の一節をもとにしているのは既に各所で語られていることですが(このイベントに昨年時点で来てた人はそのとき聞いてたりして)、名前はすべてのキーワードになり得る、と木原氏が強調。名前そのものに神が宿り、アメリカでは名付け親を“ゴッドファーザー”と呼ぶ。フィクションでもここが決まるのは大事。
ここで、トキの名前のもとにもなった八雲の日本語について。よく学んだけれど、やはり文法の理解が難しかったようで、八雲の日本語はあまり助詞がなく、“寒くない”を“サムイ”“ナイ”のように、やや英語のような文法で話し、書く際にもそうしている。しかし、セツも八雲に対しては、同様の日本語を用いていたそうで、後年、息子の一雄が著した文章には、「両親の会話が解らなかった」という証言もあるそう。
凡氏は、セツと直接会ったことはないものの、繋がりを意識したきっかけがある。それは実家にあった姿見で、幼少の頃、凡氏はこれにサッカーボールを当てて罅を入れてしまった。怒られることにヒヤッとしながらも、このときしげしげと眺めた姿見が、右側だけ褪せており、それがセツが生前、長らくこの姿見を大切にして、使うたびに拭くため持ってきた布巾を右側にかけたため、右側がより褪色したんだそうです。
そして、セツを巡るエピソードで重要なルーペについても言及、このルーペは、今は図書館がある城の北側あたりに軍事演習があり、近くの花畑で幼少のセツが遊んでいたとき、フランスの将校ワレットが近づいてきた。他の子供たちが逃げるなか、セツだけが堂々と接し、ワレットは彼女の頭を撫でて、このルーペをプレゼントしたという。このことでセツに、外国人に対する抵抗が薄れたことが、のちにラフカディオ・ハーンという人物に対して抵抗を抱かなかった理由であり、もしかしたらこのルーペがなかったら、二人の縁はなかったかも知れない。このことはセツ自身の言葉としても残され、そして肝心のルーペも現存して、現在開催中の小泉八雲記念館における小泉セツの企画展にも展示されている。
ちょうどこの怪談談義の前日、ドラマ第5回でも触れられた八重垣神社のエピソードも然り、そのときは何気ない出来事でも、のちに大きな出来事と繋がり、あれが必要だった、という認識によって語られ残っていく。こうした出来事からも、八雲とセツの一種運命的な繋がりを感じる。八雲にとって、セツという人物がどれほど貴重だったか、は別の手紙の冒頭に“世界一のママさんへ”などという言葉が臆面もなく記されていることからも解る。
ドラマでは「学がない」という自嘲が冒頭から出てきましたが、その実、語り部としての資質は優れていた。実母は有名な器量好しである一方、肝の据わった性格であり、多芸だった。文芸にも芸能にも通じていたといい、血の繫がりを感じさせる。
話は八雲とセツの馴れ初めにも及びます。八雲は松江を愛したものの冬の寒さにやられ、重い風邪を引いた。当時ひとり暮らしだったハーンですが、外国人ということで看病する者もなく、かつて八雲が滞在していた旅館の人物が紹介したのがセツだった。このとき、ハーンはセツに語り部としての資質を見出し、やがて生涯の伴侶となる。
木原氏曰く、このときセツがハーンに初めて語った怪談が《鳥取の布団》だったことに衝撃を受けたそうです。《鳥取の布団》は貧しい兄弟が、もはや売るものもなく、最後の財産であった布団までも奪われ、寒い冬に命を落とす。質屋に売り捌かれた布団からは、夜毎「あにさん、寒かろう」「お前、寒かろう」、と囁きあう兄弟の声が聴こえる、というのが大雑把な骨子。しかし、今の説明に“鳥取”の言葉がなかったように、鳥取以外でも成立しうる。恐らくハーンはその普遍的な共感性だけでなく、この恐怖よりも悲哀の強く滲むこの話を選んだセンスに、セツの語り部としての才能を見たのではないか、というのが木原氏の見解。
セツに関する資料は最近でも新発見があって、例えばセツの最初の夫で、貧乏暮らしに嫌気が差して稲垣家から大坂へと逃げていった人物が、その後岡山で運送会社を立ち上げ成功しており、直接会った人もいるんだそうです。
――といったところで前半終了。「物販で何か買わないと呪われます」と木原氏に言われたので、喉を潤しがてら、夏みかんのソーダと、きのう触れた、あの雪女さんが売っていた芳一ちぎりマシュ饅頭をひとつ購入。ソーダは講演中もこそこそ飲んでたけど、饅頭は手をつけるタイミングがなく、これを書いている現在、まだ横にそのまんま残ってます。賞味期限はまだ先なので、家に帰ってから食おう……。
ひと息ついて、後半です。
凡氏いわく、セツへの注目は2022年くらいから大きくなっていたそうです。八雲よりもセツに焦点を合わせた小説が複数登場し、山陽新幹線では車内紙に20ページを超える特集が組まれた。
セツが著した『思い出の記』は、生前の八雲と親交が深いエリザベス・ビスランドの働きかけが大きかったという。遺族の生活を心配して八雲の書簡集をまとめその印税を遺族に提供するほどだった彼女が提案、最初は渋ったセツは、三成重敬が聞き取りをすることで承諾した。それでも不安があったため、長男・一雄が坪内逍遙に託して確認してもらったところ、「妻と共に落涙しました」という反応が返ってきて、安心して発表したという経緯があるそうです。
実はここには色々ととんでもない縁がある。三成重敬は、ほとんど名前は表に出ていませんが、六法全書の編纂や、東大に今も残る歴史書にも携わっているそうです。一方で坪内逍遙は文学界の巨人であり、その影響で多くの文豪が誕生している。とりわけ、自身の新しい文学を模索していた二葉亭四迷に、「落語の書き取りをしろ」と言い、それが『浮雲』から始まる言文一致体の誕生を促した。つまり、聞き書き、という形で言文一致体を先行したセツと三成重敬に、言文一致体の誕生を促した坪内逍遙が繋がっていた、ということになる。というか、出てくる名前がビッグすぎるぞこのくだり。そしてそもそも、この言文一致体に繋がる方法論を、八雲とセツが再話文学という形で更に先取りしていたとも言える。
ちなみに八雲と坪内逍遙は早稲田奉職時代の同僚で、日本文学についての指導を求めた八雲に、逍遙は丁寧な図説を用意してくれた。もし八雲が長生きしていたら、この交流によって、また他の文芸を育んでいたのかも、と凡氏。
ここで木原氏が、前述した八雲にとっての最初の衝撃となった《鳥取の布団》に絡めて、自身のこんな話を持ち出した。多数の人々に取材を重ねる木原氏にとっては誰もが語り手、なのですが、やはり怪談に開眼する最初のショックを齎した話がある。それは小学生の頃、夏休みを前にした授業で、国語の教師がチョークを黒板に置いて、ある話を始めた――その話は、木原浩勝・中山市朗共著『新耳袋 第一夜』《第二話 仏壇の間》です。太平洋戦争の末期、多くの家族が出征して家を空けており、その教師の家には祖母と母、そして年離れた兄しかいなかった。夜更け、ふと目が覚めると、隣に母がいない。トイレかな、と探すもいない。考えて、もしかして、祖父母がお勤めを欠かさない仏壇の間にいるのでは、と思い、向かうと祖父母や母だけでなく、兄もいる。お前も一緒にお勤めをしよう、と言われ、並んで仏壇に向かい念仏を唱えていると、いつの間にか明るくなっている。もう朝か、と思い仏間を開けると、外は空襲によって一面の焼け野原だった。お陰で教師は教壇に立ち、木原氏たち生徒に話すことができる。敬虔な祖父母は仏のご加護、といっていたけれど、自分は戦地に赴いた父たちが助けてくれた、と感じている。
他の生徒は凄い話だった、と感心する一方で、木原氏は、神仏を崇める人々が大勢いる中で何故彼らがこういう形で救われたのか、そのことを不思議に思い、そこに木原氏が怪談を追う上での土台が作られた。本人が見たもの、感じたことにこそ不思議、怪異があって、それを幽霊だと思ったり、呪いや祟りだと捉えるのは、受け取る側の解釈に過ぎない。
その後、不思議なことの捉え方とアプローチが近い小泉八雲に共感した木原氏は個人的にアイルランドを複数回訪問、やがてゴールウェイの大学でアニメを題材にした講演のオファーを受けて現地へ赴き、このことが縁で在日アイルランド大使から小泉八雲四代目の存在を知らされ、凡氏と接点が生まれる。この木原氏にとって願ってもない対面と対談を、折角なら多くの人に観てもらいたい、という考え方から松江怪談談義は始まったそうです――最近忘れてましたけど、確かに私も新耳袋トークライブで聞いた覚えがある。松江を“怪談のふるさと”として売るアプローチもこのとき木原氏から提案され、色々なことが動き始めており、その大きな結実のひとつが『ばけばけ』であり、奇しくも松江怪談談義10回目と重なったことが感慨深い――今年が10回目となったのは、途中にコロナ禍が挟まったせいでもあるのですが、それもまた奇縁。
……話はもうちょっと続きますが、だいたいフォロー出来たようですし、書けないことも含まれているので、まとめはここまで。でも、これだけは書いていいと思う。自身にとってのセツがあらゆる人である、という木原氏に、凡氏が「木原さんにとって怪談とは?」と問いかけると「怪談とは、みなさんの心です」と返した。怪談を聞く形、語る形は(話に誠実であれば)様々でいい、と思うけれど、木原氏らしい答だと思います。
イベントのあとはサイン会。私も、どうにか選んで買った2冊にサインを頂戴しました。そのあと、木原さんのマネージャーの方に在宅透析について熱弁してしまったので、会場を出るのが思ったより遅くなってしまいました。またぞろ雨がぱらつく中、水燈路の灯りを頼りに、松江城をあとにするのでした。
なお、かなり走り書きのメモを手懸かりに、思い出しながら書いているため、まったく正確ではありません。また、なまじ私自身も色々読んだり考えたりしたことのある内容のため、ちょこちょこ私の解釈や予断が含まれているはずです。そのあたりはご容赦下さい。
昨年も鼕行列1を前に、松江城大手前広場や参加各町会の一画で“鼕”と呼ばれる太鼓を打ち鳴らす“鼕まつり”が実施されていましたが、今年もこの松江怪談談義とまったく同じ日に催されている……まさか、これに合わせて日程決めた?
が、松江怪談談義冒頭で「鼕まつりは中止となりましたが、水燈路は行っています」と案内があって、ちょっと落胆。直前に雨脚が強くなったのが決め手だろうか。あの、無数の灯りの中で大勢の人々が鼕を鳴らし、笛や声ではやし立てる光景が楽しみだったのですが。
が、食事のためにカラコロ工房を目指して歩いていると、遠くから低い響きと囃す声が聞こえる。近づいてみると、幸橋という、堀にかかる短い橋の近くで、建物の1階部分にある車庫らしきスペースで叩いていた。準備をしたのに、叩けないのは収まらなかったのでしょう。食後にもう一度覗いてみたら、一部かなり酔っ払っていたようですが、楽しそうでした。
食事は昨年に続きカラコロ工房のラーメンゴイケヤ、注文したのは、『ばけばけ』な放送開始に合わせて、カラコロ工房フードホールの各店で用意した、小泉八雲をテーマにしたメニューのひとつ、食人鬼のマッグロしじみラーメンです。なかなかユニークな見た目ですが、美味しかった――詳しくは別項にて記します。

第1回松江怪談談義の際に製作された琴平電鉄のヘッドマークを挟む小泉凡氏と木原浩勝氏。
- 一発で変換してくれるATOKありがとう[↩]


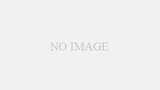
コメント